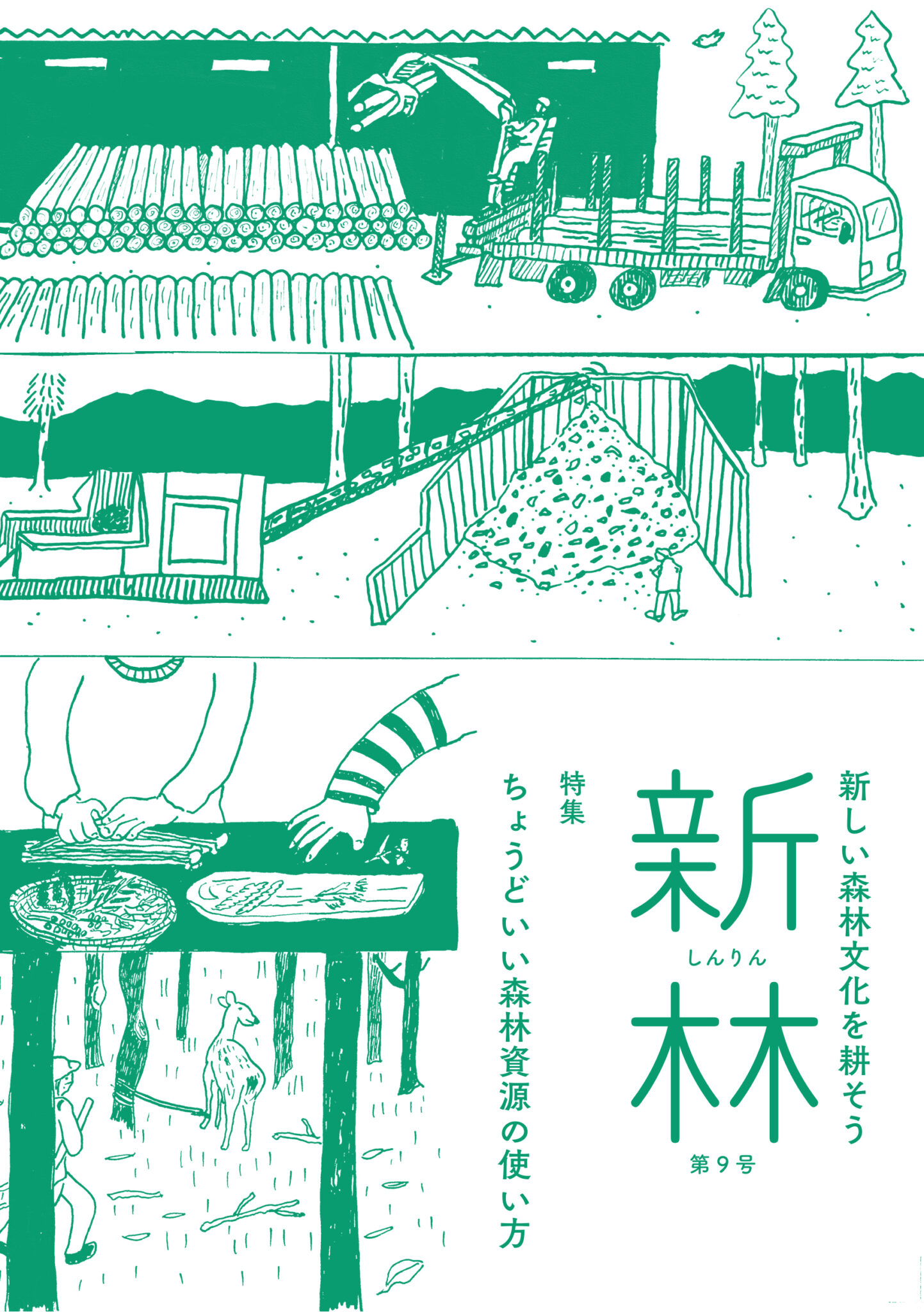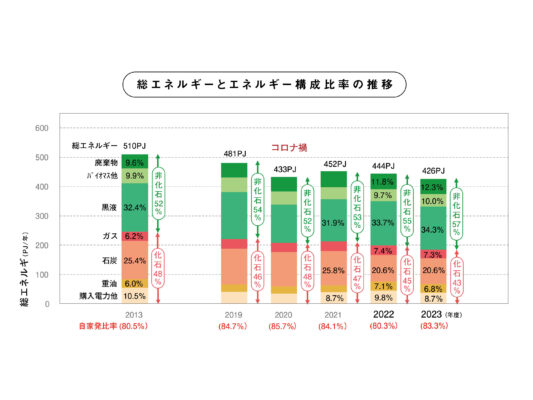「阿蘇小国の森」のストーリーを伝える小国町森林組合 後編

全国でも珍しい事業展開で小国杉の魅力を発信している、熊本県阿蘇郡の小国町森林組合。その力強い発信力は、どのようにして培われてきたものなのでしょうか。前編に引き続き、小国町森林組合 企画販売課の梅木孝浩さん、入交律歌さんを訪ね、小国杉を「育み・つかう」文化についてお話を伺いました。

小国町森林組合 企画販売課 企画販売課長 梅木孝浩さん
熊本県阿蘇郡小国町出身。1994年入組。山側の仕事、市場の仕事を経験後、2017年から企画販売課に異動。山で培った知識を活かし、製品開発に従事している。

小国町森林組合 企画販売課 企画係長 入交律歌さん
高知県出身。大学で森林政策を専攻。広告や観光の仕事を経て2012年に小国町に移住し、森林組合に入組。小国杉の魅力や森のストーリー、小国町で暮らす人たちの想いを発信している。
林業というストーリーを描く森林組合

森林組合が商品を開発して販売まで手がけるというのは一般的なことなのでしょうか?
梅木さん 森林組合によって、川上から川下までの流れの中で、どこまでを担うのかは違いがあります。市場を持っていない組合は、山から生産した木を原木市場に持っていくところまでが組合の仕事ですね。市場があれば原木を販売するところまで、製材所や加工所を持っている組合であれば、製材・販売するところまでが組合の仕事になります。小国町森林組合が他と違うところは、企画販売課を設けて、川下の企画・製造・販売を行うことですね。小国杉に高付加価値をつけて、単なるものの販売だけではなく、林業というストーリーとして、パッケージで活動しています。

小国町森林組合は、森林整備課と企画販売課と総務課、そして地籍調査課の総勢34名(2025年4月現在)。小さな組織ながら、川上から川下までさまざまな経歴を持つ職員が集まっています。
梅木さん 組合長は小国林業の始まりのシンボルである樹齢270年の山を継承する山主でもあるので、山側の想いが組合に届きやすい環境にあると思います。私自身は、森林整備課の仕事を長く経験してから8年前にこの企画販売課に異動しました。異動するまでは山から出した原木をランク分けして並べていただけで、その先に考えが至らなかったのですが、今はこの商品をつくりたいなら、こんな木を伐ってこないといけないね、という逆の見方ができるようになってきましたね。
入交さん 私は広告や観光の仕事を経て、2012年に小国町へ移住して森林組合に入組しました。じつは大学で森林政策を専攻していたのですが、学生の頃から大学での研究成果が一般社会に向けて上手く伝わっていないと感じていました。そこでいつか山に戻り、地方の良いところを伝える仕事がしたいと思いながら、いろんな仕事をしていました。
川上から川下まですべての人の想いをつなぐ森林組合

入交さん 実際に山で働いてみると、たとえ山の管理であっても人間相手の仕事であり、大学で学んだ通りにはならないということを思い知らされます。例えば、原木が川下に渡るまでの間を抜いてしまえば、マージンが全部山に入るじゃないかといった考え方もありますが、物事はそんなに単純な話では無いんです。山主さん、伐る人、運ぶ人、皆さん人間なので、正論の前に「やりたくない」という気持ちでやれないことも沢山あります。そこを職員が山主さんや買う人の気持ちを汲み取ったり、間に入って取り持ったりしながら山の施業を行なっているということが良く分かりました。

私たちの仕事は山から木を出してただ販売するだけではありません。270年続いてきたこの町の林業や、山に携わってきた人たちの想い、地域でものづくりに携わる職人さんの誇りをお話して、共感していただけた結果、物を受け取ってもらえる、というような小国杉のあり方を目指しています。
そのため、小国町在住の木工作家さんたちと連携し、阿蘇くまもと空港内に小国杉の家具ゾーンを設けたり、引退される木工職人さんのお弟子さんと木工所の機械ごと森林組合で引き継いだりと、川下の木を使う文化の継承にも力を入れています。
小国杉を「育み・つかう」文化

小国町森林組合が、他の森林組合にはない、独自の接点づくりや川下に関わる分野まで手がけるようになった1番大きなきっかけは何ですか?
入交さん きっかけは、おそらく80年代に建てられた小国町の公共施設〈道の駅小国ゆうステーション〉や、それに続く〈小国ドーム〉など一連の木造建築群だと思います。

小国町では、当時の町長であった宮崎暢俊氏の「林業地自らが流通から加工までを行い、積極的に木の活用をすることが林業の活性化につながる」という考えのもと、まちづくり構想「悠木の里づくり」がスタート。町内の公共建築に小国杉を積極的に使用すると同時に、木の文化を復活し、小国町を個性的で活力のある町にするための施策が進められました。
入交さん 〈道の駅小国ゆうステーション〉や〈小国ドーム〉など、木造建築群の多くに小国杉の間伐材を利用した木造立体トラス構造が採用されましたが、当時の建築基準では、あのような細い間伐材のトラスで巨大な建物を建てた前例がありませんでした。そこで国立林業試験場で国内初の地域材強度試験で、国の木造設計基準数値を大幅に上回る結果を出し、特別に大臣の許可をもらって建設されることになりました。

入交さん 小国ドームの時代から小国杉を使った地域デザインに取り組んできた結果、町には自然と調和した看板や小国杉を使った不思議な建物が点在するようになりました。小国町へ移住してきた方の中には、小国町の「木のある」暮らしや景観を気に入って移住を決めた方もいます。移住者の新たな視点で小国杉の魅力を発信していただいた事例も多いですね。
梅木さん そして地元の人間も、地域資源を活用するためにさまざまなチャレンジをしてきました。森林組合では製材所から出たチップを固めて壁材を作ってみようとか、組合の倉庫に木タイルとして使えないかとか、U字溝の蓋にならないかとか、いろんな事をやってきたので、チャレンジするのが当たり前という風土がその頃から培われていたと思います。
入交さん アロマオイルづくりも、移住者の私が提案するなら、いかにもありそうな話ですが、じつは森林組合の偉いおじさん達が言い出したことなんです。〈Layer〉の時もそうですが、「また小国町森林組合が変なことして」と言われるのはいつものことです。そんな企画販売課の取り組みに対して、山の施業を行う森林整備課の保育林産班の人たちが「こういうことしているのはうちの組合だけだよね」ってちょっと誇らしく言ってくれるんです。それがとても嬉しいですね。
取材を終えて、帰りに立ち寄った小国ドームでは、木のドームに囲まれた大きな空間の中で、地元の子どもたちがバスケットボールの練習をしていました。この日常の風景は、すべて小国町の人たちによって守られてきたもの。阿蘇小国の森が生まれて270年、「悠木の里づくり」宣言から40年。「文化」とは、人が絶えずつないできた想いの連なりなのだと、改めて感じました。(2025年3月13日 現地取材)