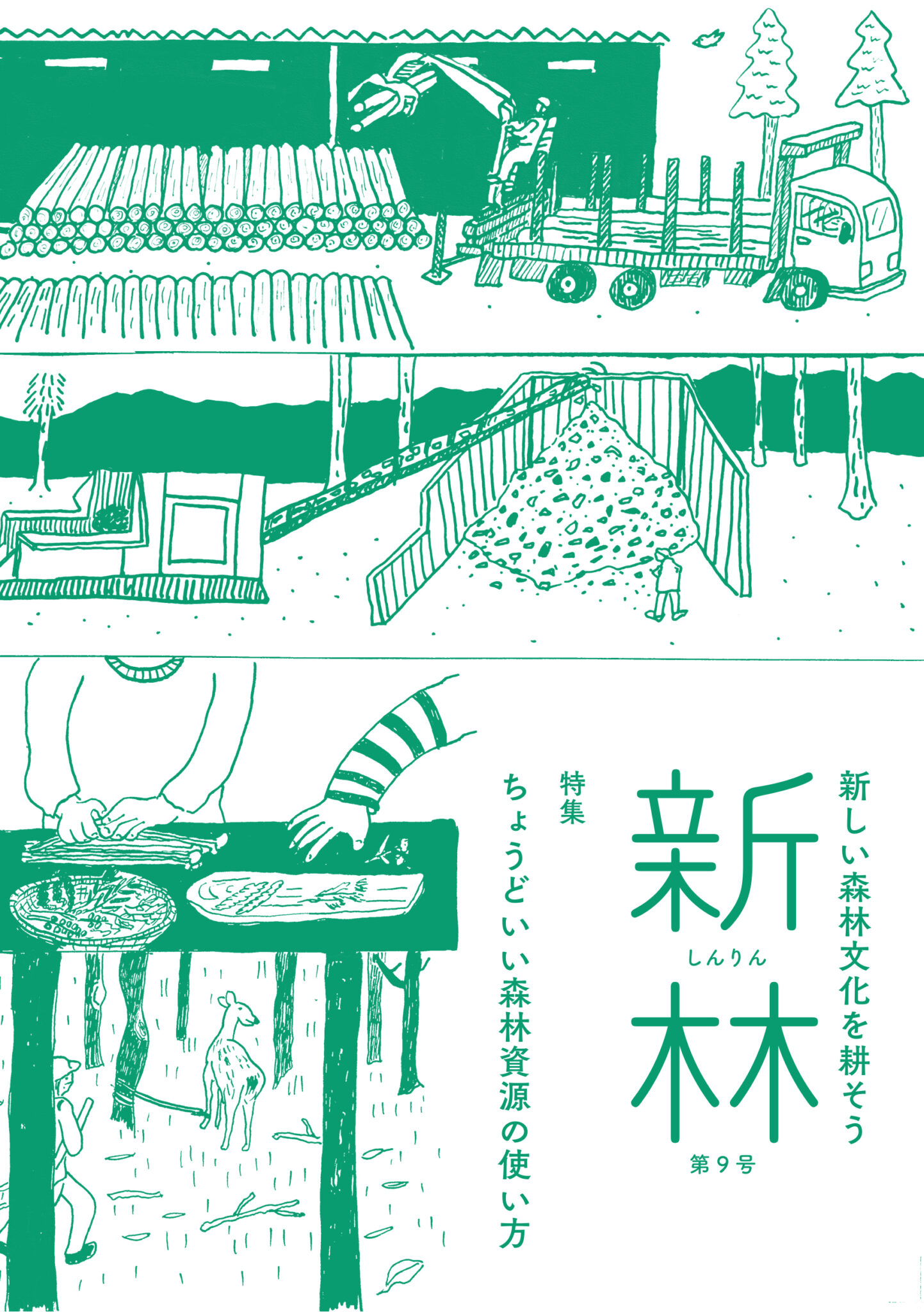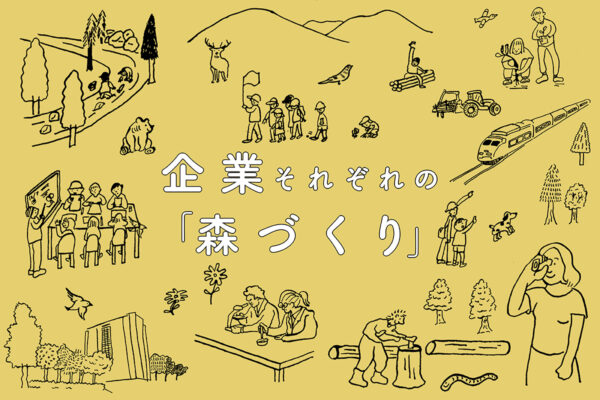年の瀬の山仕事と祈りの植物 / 鈴木将之さん、鈴木蒼真さん

新年を迎える家々に飾られるお正月飾りは、山から降りてくる歳神様をお迎えし、おもてなしをするためのものだそうです。山々は、古くより日本人にとって神聖な場所。神様にお供えする植物もまた、山に自生するものが多くあります。今回は、静岡県浜松市天竜区の鈴木将之さんの山を訪ね、お正月飾りや神前、仏前に供える植物と、年の瀬の山仕事についてお話を聞きました。

鈴木将之さん
自伐林家。鈴木家12代当主。天竜で代々農林業を営む家に生まれ育つ。天竜林業研究会会員。60haの所有山林で杉、桧の育林、生産をしながら、山にある林産物を生かした多角的な経営を展開している。
「山眠る」季節の山仕事

「山眠る」という冬の季語は、葉を落した枯山の姿や雪に包まれた静かな山、冬眠する動物たちを連想させます。実際に冬の植物は、常緑樹のスギやヒノキも休眠状態となり、厳しい寒さに耐えながら春の訪れをじっと待っています。とはいえ、すべての冬の山が静寂に包まれているかというと、そうでもないのです。人工林の多くは、木が休眠状態に入り、水分を減らした冬が最盛期。人間だけは冬の山で忙しく活動しています。

12月19日、静岡県の天竜で江戸時代から続く鈴木家の山もまた、一年で最も忙しい時期を迎えていました。先祖代々、丁寧に手を入れて守られてきた山には、NCMの木こり活動でお世話になっている講師の前田さんが「これぞ天竜美林」と称する、美しいスギ・ヒノキの人工林が広がっています。しかしこの日、山からチェンソーの音を聞くことはありませんでした。年の瀬が押し迫る12月の後半だけは、スギ・ヒノキの伐採を一時休止して、お正月に向けて榊(サカキ、以下サカキ)や樒(シキミ・シキビ、以下シキミ)の収穫を家族総出で行うそうです。
将之さん「昨日、奥さんと温泉に行ってきたんですよ。これからいよいよサカキとシキミの繁忙期。大晦日まで収穫と出荷に追われるので、その前に英気を養ってきました。我が家では一年を通じて奥さんがサカキを、息子がシキミを育てて出荷していますが、今の時期は山に自生するセンリョウも収穫して出荷しています。この辺りの地区ではお正月飾りのウラジロも出荷していますが、うちではここ数年サカキとシキミが忙しく、ウラジロまで手が回らなくなっています」
家族で守り育てる山

シキミを担当する蒼真さんは現在23歳。家業を手伝う蒼真さんにとって、山や家業はどういった存在なのでしょうか。
蒼真さん「僕と両親は山を下りたところに住んでいるので、僕にとってこの山は祖父母の家がある場所。こういった環境に育って良かったなと思っていますが、私生活の趣味はまた山とはぜんぜん違いますね。山の仕事を手伝うようになってからは、父親が職場の上司ですが、うちは父が基本優しいので、ギクシャクすることもないですし、自分のペースで仕事ができるのも楽しいです」

蒼真さんの横で「父親が厳しかったので、自分は息子にあまり厳しくできないんですよ」と話す将之さん。〈ずっきー’s〉というロゴが入った家族お揃いの服を着て作業をするお2人の姿は、今時の父子の姿そのもので、勝手に抱いていた「山仕事=厳しい世界」というイメージからはほど遠い。
神前に供える榊(サカキ)

サカキは、神様の領域(神域)と人の領域の境目に存在する「境目の木」、常に葉が緑で「栄える木」といった意味があり、神棚のお供えや、神事で玉串を神前に捧げる玉串拝礼(たまぐしはいれい)に使われるなど、神道の儀式に欠かせない植物です。家庭では1日と15日に新しいサカキをお供えしますが、特に年始に向けて出荷のピークを迎えます。

将之さん「じつは去年、下の川沿いの道から山へ上がってくる道が崩れ、車が通れなくなったんですよ。そのため山の木も1年ほど出せない状態でした。うちではそうしたリスクを分散するため、サカキを何箇所かに分けて育てていて、今後シキミも植える場所を増やしていく予定です。ただ山の上のこのサカキは、神社の柱として出すような樹齢100年以上のヒノキ林の中に生えているので、自分の中ではより神聖な植物に感じています」

「普段はこんな場所では束ねないんですけどね」と言いながら、束にする様子を見せてくれた将之さん。サカキは枝が左右に広がり平たいのが特徴で、束にする時も平らに重ねていきます。
将之さん「僕はこういった作業のセンスが全くないんですよ。息子の方が上手いですし、奥さんは僕の3倍くらいのスピードで美しく仕上げますね」
お正月の縁起植物

お正月飾りでよく用いられるセンリョウは、10月から2月にかけて真っ赤な実をつけます。センリョウは、マンリョウや南天など、他の赤い実をつける植物と同じく、厄除けや商売繁盛、子孫繁栄など縁起植物として知られています。山に自生するセンリョウを毎年お正月用に出荷するという将之さんに付いていくと、赤い実が見当たりません。

「この辺りはほとんどなくなっていますね。鳥に食べられたのかなあ」
シカだけでなく、鳥も油断できない山の中。ウラジロはというと、「繊維が多いのでシカはウラジロを食べないんですよ」という将之さんの言葉のとおり、ヒノキ林の足元一面に繁茂していました。

ウラジロはその名のとおり、葉の裏が白く、羽のような葉が左右対称に向かい合っています。その色形から清廉潔白を表し、長寿や夫婦円満の縁起物としても知られています。また古くから、先祖の霊が宿っている場所と信じられており、お正月には先祖の精霊をお迎えするときに飾るようになったと言われています。

将之さん「お正月飾り用に収穫するには、5月頃に下草を刈っておく必要があります。そうした下準備をしておくと、年末に丁度良い大きさに育ったウラジロを収穫することができるんです」
仏様に供える樒(シキミ)

仏前にお供えするシキミも、新年に向けて出荷が増える植物です。素人目にはシキミもサカキも似ていますが、シキミは仏事、サカキは神事に供える植物です。鈴木家のシキミは、元々茶畑だった日当たりの良い斜面に植っています。天竜ではシカによる食害が深刻ですが、小高木のシキミはシカに食べられることなく、ツヤツヤとした鮮やかな緑の葉を茂らせています。
将之さん「シキミは毒があるので、シカに食べられないというメリットがあるんですよ。でも最近のシカは毒があるものも食べるようになってきたみたいなので、もしかしたらシキミも食べているかもしれませんね」
シキミが持つ独特の香りには、防臭・殺菌・防虫の効果があり、土葬が一般的だった時代には、故人を獣や邪気から守るためのものとして重んじられてきました。今では仏前や墓前にお供えする植物として、またお線香や抹香の原料としても使用されています。

仏前に供えるお花を「香花(こうばな・こうげ)」と言いますが、店頭ではシキミが「香花」として並んでいるのをよく見かけます。店に並ぶ姿に加工するのも蒼真さんの担当です。
蒼真さん「普段は収穫したものを作業場に持ち帰って切り花として加工し、出荷しています。シキミやサカキは枝葉の整え方や、全体の長さが大事なんです。シキミは悪い葉や余分な葉を落とし、左右バランス良く『ひし形』に整えて、4〜5本の束にします。お墓や仏壇にお供えするので、花入れに合うよう枝の長さも調節しています」
山を守り育てるために

サカキやシキミ、お正月飾りで使う植物の出荷は、スギ・ヒノキの造材とはまた別のやり甲斐があると言います。
蒼真さん「地元のファーマーズマーケットなどに出荷したサカキやシキミは、その日の昼に1回、晩にも1回売り上げが出るんですよ。山仕事は時給とかじゃないので、自分の頑張りがすぐに数字で反映されて分かりやすく、やっていて楽しいですね」

将之さん「自伐林家だと、山仕事ってほぼ一人仕事なので、自分のペースでやれる良さもありますが、一人寂しく山の中で粛々と作業するばかりだとつまらないじゃないですか。サカキやシキミは収穫から加工、出荷まで行いますので、品出しの時にお客様からもっとこうして欲しいとか、こんなの無いの?と言われたりして、お店の方やお客様と対面して商品の反応を直接確認できるのが面白いと思います」

将之さん「同じサカキでもお供えの仕方や神事によって色々な形がありますし、花屋に出荷する花木はお店の方の要望に合わせて商品を開発したりする楽しさもあるんです。そこが木材の出荷と一番違うところですね。木材は基本市場に出すので、値段は市場で決まりますし、出した木がどこでどんな風に使われるのか分かりません。サカキやシキミは自分たちで商品の開発もしますし、値段も自分たちで付けます」
伝統ある鈴木家の山を将之さんの理想の姿に近づけ、守り育てるためにも、サカキやシキミの栽培は大切な収入源となっています。年末まで収穫を続け、年が明けたらスギ・ヒノキの伐り出しを再開。鈴木家の冬の山仕事はこれからさらに忙しくなりそうです。
(2024年12月19日 現地取材)
関連記事

天竜の森で植林について考えてみる
[木こり活動レポート #4] 300年以上続く天竜の森へ 2021年11月12日、木こり隊は静岡県浜松市天竜区で300年以上続く鈴木家の森にやってきま …

山暮らしの道具 KISSA山ノ舎 中谷明史さん
[森林の資源をつかってみる〈インタビュー〉 #2] 山の暮らしは楽しい?大変?家族で山へ移住した中谷さんの暮らしと、山の必需品について聞いてみました。

お赤いのがお好き
[森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~ #3] 植物生態学者・柳沢直教授によるエッセイ。

初心者にもオススメ!?シダ植物調査をしてみよう ①シダ植物ってなんだ?
[ちぐさ研究室の研究日誌 #8] 連載第8回のテーマは「シダ植物」