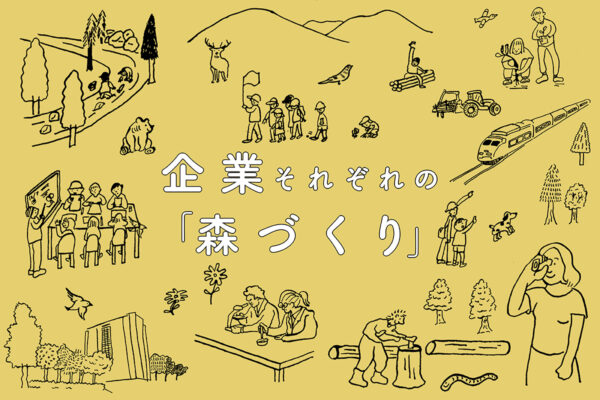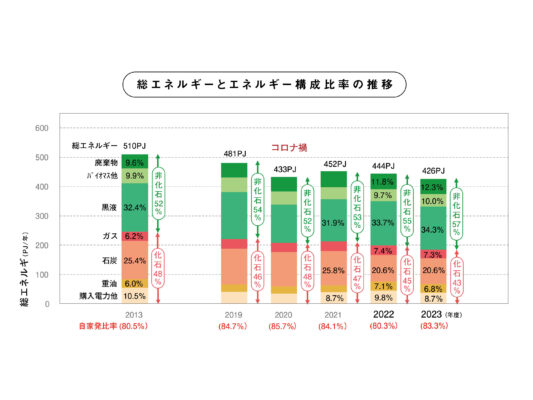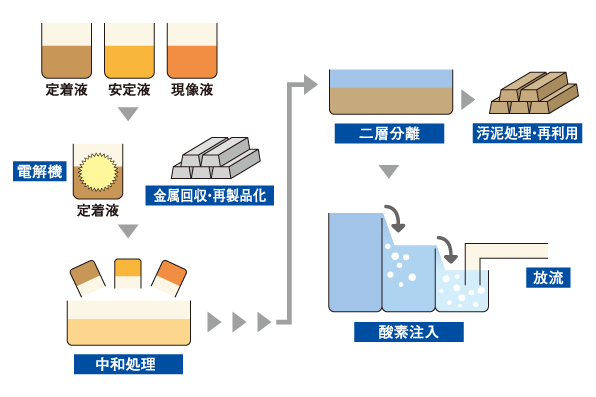アートと山の「わからない」
「ART in 鳳来寺山ろく」レヴュー

愛知県新城(しんしろ)市。県の東側に位置する、緑豊かな小さな町である。かつて長篠の合戦が起こった歴史ある土地でもある。今年10月、この町のかつて鳳来町(ほうらいちょう)と呼ばれた、山奥の地域で展覧会が開催された。その名も「ART in 鳳来寺山ろく」。会場は廃校となった旧門谷(かどや)小学校で行われた。会期は10日から14日の5日間。本企画は「山が開く言葉」と題して鈴木孝幸さんと大和由佳さんの作品展示のほか、自然を意識したワークショップ、ゲストを呼んでのトークショーなどもあった。私は10月12日(日)のトークショーのある日に参加した。以下はその時の記録とレヴューである。

筆者|荻野斗樹
愛知県豊橋市で生まれ育ち、高校から新城市に移り住む。大学は名古屋の方の芸大に進み、デザインプロデュースやソーシャルデザインなどを学んだ。卒業後は岐阜県で林業会社に就職し、現在はまた新城の実家にいる。芸大といっても専攻はデザインで、林業会社も1年半しか勤務していない。アートも山のことも知識は中途半端だ。
[目次]
門谷小学校と「ART in 鳳来寺山ろく」について
Ⅰ. 山のこと、門谷のこと
Ⅱ.アーティストが場を開くこと
Ⅲ.この際、拝戸さんに聞いてしまおう
「自分ごと」が「わからない」から解放されるヒント
門谷小学校と「ART in 鳳来寺山ろく」について
門谷小学校は明治5年に開校し、大正14年に現在の建物が建設され、昭和45年に閉校した。その後紆余曲折あり、2014年から地元出身のアーティストの鈴木孝幸さんがここでの展示を始めた。2024年に一度休止したものを抜けば、今年で10回目の開催となる。

まず驚いたことにこの展覧会は全て寄付で行われている。補助金も特に使われていない。国際芸術祭「あいち2025」とも時期は重なってはいるが、それとは関係ない完全な自主企画である。校舎内には鈴木孝幸さんと大和由佳さんの2名の作家の作品が展示されていた。






美術館やギャラリーで鑑賞することと違い、古い校舎の床の軋みとしっとりとした湿気を肌身に感じながらの鑑賞となる。光もスポットライトではなく窓から差し込む自然光で、大きな窓の校舎だからこその優しい明るさだった。個人的にはホワイトキューブの中で緊張して観るより、落ち着いて作品を見ることができたように思う。時たま、都市で見ないような大きな虫がいたり、作品に蜘蛛が巣をかけていたりと、山間地ならではの体験もできる。
心なしか大和さんの「蜘蛛とeveryone」という作品と連想してしまう。

Ⅰ.山のこと、門谷のこと
不思議な関係
この日最初のトークショーは鈴木さんと門谷小学校の管理人の山下修市さんで行われた。ファシリテーターとして、新林執筆者山川さんも参加した。
山川さんとお二人の関係は以下のURLから
https://sin-rin.jp/new-forestory/do/4838
https://sin-rin.jp/new-forestory/do/5231
山下さんは製材業を生業としており、「森林真剣隊」というNPO法人を近隣住民と立ち上げ、山林の問題にも取り組んでおり、山に対する知識が豊富な方である。一方で美術に対しての造詣はそこまで深くない。しかしこの場の提供に協力し、トークショーにも登壇し、鈴木さん、山川さんともよく議論をすることがあるらしい。この関係性は一体なんだろう。はじめにその疑問が浮かんだ。
結論は無し!
話の流れから、山を見る、アートを見るとはどういうことか、どういう共通点があるのかという問いが立てられた。だが山川さんははじめにキッパリと「結論はありません」と語った。結論はでないが、こういう問いは答えではなく、その過程が大切なのだろう。
この写真から何を思う?
トークショーは一枚の写真から始まった。校舎の裏山をとらえた写真である。

これを見て何を思うか。そんな質問だ。鈴木さんは、新緑や空の青さと、自身の作品のテーマである土砂崩れから斜面に、山下さんは木の種類に注目していた。奥の方が針葉樹、手前側が広葉樹の典型的な放置林だという。やはり知識がある分見方が素人とは全く違う。
山川さんはアートに対しても同じだと語る。知識やよく見る姿勢があれば、「わからない」と言われるアートももう少し見え方が変わってくるのではないか。裏を返せば、山のことをよく知らない我々は、山下さんほどしっかりと山を見ていないのではないか。そう提起する。
自然とは人工とは
続いてとある里山の写真が画面に映された。山下さんは一発でその地域の名前まで特定した。山を切り拓いた土地であり、周りの木々は人工林である。写真には段々畑が写っていたが、それは戦前に作られたものらしい。そもそも里山とは人間の都合で切り拓かれた場所である。そうなると我々が普段「自然」と呼んでいるものの中には人の手が関わったものが数多くある。人間は果たして「自然」に住んでいると言えるのだろうか。鈴木さんの作品の中にはモルタルや鉄などの素材が使われているものも少なくなく、それがこの場ではとても印象的だった。まさに、自然と人工の定義が揺らぐ作品群と言える。山奥で行われる展覧会であれば、天然の素材ばかり用いられるイメージをどうしても持ってしまっていた。しかし、そもそも一体何が自然で何が人工なのか、人の手が入ってしまえばそれは自然でなくなるのか、と考えていくと違う視点からモルタルや鉄などの素材を見ることができる。


Sculptureシリーズの彫刻は、地面に根を張る植物と、モルタルの中に張り巡らされた鉄筋とを連想した作品となっている
続いて、鈴木さんは山の中を流れる川も、人の手が加えられていることに触れる。静岡には天竜川という大きな川が流れているが、そこと愛知の宇連川(うれがわ)とは地中でつながっているのだという。
そしてその水は豊川用水として愛知県の農業生産に役立てられているという。我々の生活は見えないところで自然とつながっており、自然の方も一見すると人の気配がないようで、さまざまなところで人の手が入っている。校舎の入り口からグラウンドをまっすぐ通り、校門まで続く樋は、それらを意識したワークショップを行った跡でもある。

「わかりあえない」からこその親密さ
鈴木さんと山下さんは互いをわかり合えないということがあるという。お二人の山に対する興味のあり方や問題の意識が全く違うことは、ここまでの話を聞いても明白だった。先程の写真でも、鈴木さんは色から注目したのに対し、山下さんは木の種類から考察する。前提の知識の違いにそもそも大きな違いがある。それでも10回もこの展覧会を続けられる関係性は、互いの核となる部分をある程度認めているからこそなのだろう。人と人がわかり合えるということは思ったより簡単ではない。わかり合えると簡単に口にすることは、むしろ相手のことを軽薄に見ている行為かもしれない。むしろ互いに干渉しない一定の距離感があるからこそ、尊重し合えるのかもしれない。

Ⅱ.アーティストが場を開くこと
国立奥多摩美術館館長(?)佐塚さん
二つ目のトークショーは、国立奥多摩美術館館長の佐塚真啓さんがゲストだった。国立奥多摩美術館とは、東京都青梅(おうめ)市にあるアトリエで、不定期で行うイベントの時に作った看板に「国立奥多摩美術館」と書かれていたものがそのまま名前になってしまったのだという。つまり一般的な意味での国立美術館ではない。地理も奥多摩よりはややずれるという。

過去に「芸術激流」というラフティングの会社と組み、ゴムボートで激流に流されながら河岸にある作品を鑑賞するというユニークな企画を行なっていたという。自分のペースで見る美術館やギャラリーと違い、強制的に移動を強いられる中で鑑賞するので、見落としもかなりあるらしい。そもそも「激流」という名がついてるのだから、ボートに乗ることだけでも命懸けであることが予想される。どこに作品があるかということも参加者には伝えていなかったそうだ。話に聞く限り、全く作品に没入できそうにない。私は美術館で入館料を払って観る作品は、なるべく記憶に留めておこうと、じっくりと観る癖がある。それはある意味美術館という空間と、入館料に自らが縛り付けられているのかもしれない。
ともかく、何やらとても面白い方だ。
そんな佐塚さんは元々東京で使っていたアトリエが使えなくなり、廃墟となっていた製材所を仲間と共にアトリエとして使い始めたことがきっかけで、この青梅市に来たのだという。
内部の鈴木さんと外部の佐塚さん
鈴木さんは地元出身で、今回の展覧会も地域住民に挨拶に回って実現させているという。近所に住んでいることももちろん強みだが、地域住民たちに足を運んでお願いしているというまめさが、補助金に頼らずこれだけの展示ができた理由だろう。
一方の佐塚さんは青梅市には初めから外部の人間として入り、特に地元の住民に挨拶することもなくイベントを企画したりしていたため、一時期は警察を呼ばれることもあったという。しかし佐塚さんは現在近くの山を購入し、農業も始める予定だという。そうした行動もあってか、地域の中で異端とされながらも、存在を認めてくれているらしい。むしろ、外部で居続けることが難しいのではと佐塚さん。これは、地方でのイベントや地方移住を考える人にとっては希望のある話かもしれない。
現代美術の「わからない」は「自分ごと」という態度で
現代美術に対して「わからない」と言われること。これは「Ⅰ.山のこと、門谷のこと」の中でも話題に出ていた。
佐塚さんは面白さがわかりやすく提供されているエンターテイメントと比較し、美術は鑑賞者側が面白さを引き出す手間を必要とすると語った。加えて「わからない」で感想が終わってしまう人は、作品に対して一歩寄ることを行なっていないとも。作品に対して、鑑賞者がただ受動するのでなく、自ら歩み寄り、そして自分ごととして考えるべきだと語る。鈴木さんはそもそも自身が作品を見るときにわからないことが当たり前で、わからないことに対して、自責することも気にすることも特にないと語る。
わかりやすいことは情報を理解しやすい利点がある反面、こちらが自ら考えるという過程を放棄している点があることを気をつけなければならない。一見すると理解に時間がかかる物事に対して歩み寄る姿勢は、現在において特に必要な態度ではないだろうか。芸術激流という企画も、見やすさを十分提供された一般的な展示とは対極のものである。しかしその悪条件の中で必死に何かを探すことに意味があるように思う。
Ⅲ.この際、拝戸さんに聞いてしまおう
あいちトリエンナーレの立役者・拝戸元館長
トークショー最後のゲストは愛知県美術館元館長の拝戸雅彦氏である。
話は60年代後半にイタリアで起こった芸術運動である「アルテ・ポーヴェラ」の作家の話題から始まった。アルテ・ポーヴェラは石や植物などの自然物や、鉄やビニール、廃材などの日常的な人工物などで作られることが特徴的である。日本では「貧しい芸術」として訳されることが一般的である。
拝戸さんはその代表的な作家である、ヤニス・クネリスやマリオ・メルツなどの作家のエピソードを語った。クネリスが、愛知県美術館の床の大理石を褒めたりと、およそアルテ・ポーヴェラっぽくない発言をしたこと、マリオが台湾の公園の池に石を投げると、鯉が餌と勘違いして集まって、また散ってゆく様子を、美術館に群がるアーティスト、ギャラリストのようだと皮肉を言ったことなど語っていた。
大和さんはエピソードを大変面白がっておられる様子だった。エピソードを通して作品を見ると、作品をより深く見えるという。
確かに、私はアルテ・ポーヴェラの作家たちは、資料でしか知らない。もう亡くなった作家も少なくない。しかし拝戸さんが作家との思い出話を語る際は、まるで隣にマリオ・メルツやヤニス・クネリスがいるかのような語り口で喋る。そうすると何故か作家たちが急に美術史の資料から身近な存在へと我々に急接近してくる。作品に深い共感を得る一つの方法としては、作家を身近に感じながら見るということもあるかもしれない。


自然と人間の距離
拝戸さんは動物と人間の距離はずっと縮まっていないと語った。人間が動物を躾ける時、特定の種は言葉を覚えて、檻へ入ったり、曲芸をしたりする。しかし、人間は動物の言語を理解していることは極めて少ない。そのような面から、距離が縮まっていないことを指摘する。日本人は昔からアニミズム的と言われるが、その「アニマ(魂)」はあくまで人格を自然に当てはめるようなもので、自然が独自に持っているものではないことも挙げる。
キュレーターが取るべき行動
インスタレーションや素材が意識した作品を展示する際に、キュレーターは作家と積極的に話すべきだと語った。指示書だけで設置を判断するのでなく、作家との生の会話をし、意思を理解しないと良い展示にならないという。特にアメリカの美術館の基本的なスタイルは、作家が自分の作品には触れられず、指示書に従って設置される。するとどうしても冷たい印象を受けてしまうらしい。拝戸さんがここまで作家とのエピソードを語ることができるのも、作家と積極的に会話しているからなのだろう。さらに拝戸さんは、自身がイタリア語が使えることを挙げ、もしも深い会話したいのであれば、その国の言語を喋ることができるようにしておくと良いと語る。英語圏の国以外でも大抵英語でコミュニケーション(Communication)は取ることができる。しかしそれはカンバセーション(Conversation)ではないという。

日本の美術はイタリアよりも自由?
トークショーのなかで何度が議題に挙がった、「わからない」問題。一つは美術教養などといった、美術の層の厚さが薄いことが指摘される。しかし拝戸さんは、厚さがない分、自由になっていると語る。イタリアは美術史で最重要なルネサンスの発祥の地である。しかしその重大な歴史を抱えているがゆえに、その古典からなかなか抜け出せない面もあるのだという。アルテ・ポーヴェラでも、ミケランジェロ・ピッストレットの「ぼろぎれのヴィーナス」という作品では、中央にヴィーナス像が用いられている。従って、日本はそのような古典主義的な文脈がない分、さまざまな作品のあり方を模索できるという。その文脈でいえば、純粋なアートができる土壌でもあるのかもしれない。
「自分ごと」が「わからない」から解放されるヒント
今回のトークショーと展示は、自然という言葉をもう一度捉え直す良い機会だったのではないかと思う。それがこの豊かな山林に囲まれた旧門谷小学校で行われたことにとても意義があるのではないだろうか。この小さな学校で、参加者は多くの学びを得ることができていることだろう。
都市からはアクセスに時間を要するこの地で企画を行ったということ。わざわざ労力を使いこの地まで足を運んで見てみること。それは今回佐塚さんがアートと向き合う時、「こちらから歩み寄り、自分ごととして考える」と語ったこととよく似ている。あらゆる物事に受動でなく自ら行動し知ろうとすることは、決してわかりやすくない社会を生きていく上では必須なのかもしれない。
今回の展示に大和さんの作品「新聞(パレスチナの地図とSのノート)」があった。イスラエル入植により消えてゆくパレスチナの地名を記したものである。QRコードで音声が聞こえるようになっており、発音の仕方がわかる。音声は日本に難民として来日したシリア人の方に協力してもらったらしい。その方もアサド政権の崩壊により、故郷が不安定な状態にあり、大変苦しい思いをしているようだ。
複雑な問題であり、日本から遠く離れたところで起きている惨劇に対して、私たちは何を考え、どう行動すべきなのだろうか。大和さんは、地名という日常的で、複雑でない情報を知ることで、自分ごととして考えた。
意識を日常まで掘り下げた時、例えばその日常が大きなものに脅かされた時、私たちは初めて血肉が抉られたような感覚を覚える。自分ごととして考えた時に、私たちは複雑な問題に対しての解像度が上がるのではないだろうか。
わからないに対して一歩踏み出し、自分ごととして思考する。森林や地方も問題は山積みである。私も考えることを怠らないでいきたいものである。

ART in 鳳来寺山ろく
-自然豊かなフィールドで現代美術を体験する
会期:2025.10.10金-10.14火
会場:旧門谷小学校
主催:門谷小展覧会運営委員会
http://kadoya-art.com/
Instagram @art_in_houraijisanroku