甘い幻想/辛すぎない理想① 山の現在地

物語の中の、山の印象
「山って・・・何なん?」という連載なのに、前回の連載8は田んぼの草刈りの話で終わってしまった。一口に山といっても、登山する山だけでなく、集落の近くにある森や林を指すことがある。里山だ。そこは雑木林や田畑、草原やため池、農地が含まれ、人の手が入った自然の状態を示す。
ここでちょっと唐突ではあるが、昔話の桃太郎の冒頭を紹介したい。「むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に行きました……」。こんな感じで物語は始まっていく。
昔は洗濯機は無いので、近くに流れている川で衣類を洗っていた。毎日行う家事労働だし、なんとなく情景は想像しやすいだろう。問題はおじいさんの”しばかり”だ。「昔の人は、毎日草刈りをしていたの?」あなたの脳内で、芝生を刈り取るイメージがリフレインされていないだろうか。
おじいさんの”しばかり”とは”芝”ではなく”柴”なのである。”柴”とは雑木の小枝のことで、それらを折って薪にし、かまどで火を炊いたり、家や畑の垣根として使っていたそうだ。小枝だから乾きやすく、扱いやすい。そう、おじいさんは日々の生活のため/燃料確保のため、山へしばかりに行っていたのだ。

国立国会図書館 – 山東庵京伝(山東京伝)著『絵本宝七種』、蔦屋重三郎刊、1804年。国立国会図書館所蔵(ID:000010063401 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288336)。, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75773013による
日本の山にも、変遷がある
ちなみに桃太郎は西暦1600年前後、室町時代後期のお話だと言われている。江戸時代になると生活水準が向上し、人口が増加。燃料用の木の奪い合いが激しくなり、山は荒廃、”はげ山”が広がり、土砂崩れや水害が酷くなった。その反省から、森林を育てるための林業という生業や、治水事業が始まったらしい。
さらに第二次世界大戦、戦後の復興のため、木は伐られた。山にはもちろんのこと、畑や田んぼにも杉や檜が植林され、80年かけて現在の山が形成された。そんなわけで、今の日本の山は天然林は少なく、人工林が多数を占めている。日々の燃料として木を使うことはほとんど無く、林業は担い手不足。手入れされないから、荒れ放題。日本の山は傾斜地が多いため土砂災害は起きるし、杉は伸び放題だから花粉が放出される。いろんなことを端折りまくって説明したが、こんな経緯が山にはある。
山に通い、いろんな人の話を継ぎ接ぎしていく内に、結局、今の山たる山を作ってきたのは人間の欲望なんだな、と思った。
木を伐る、草を刈る
私自身、祖父が亡くなってから放置していた期間が長かったので、当然、相続した里山は荒れていた。山の爺たちと一緒にチェーンソーや刈払い機で素敵なハーモニーを奏でたいなどと甘い妄想を持つ割には、現実は厳しい。正直、5年も放置していた田んぼの草刈りは、もう二度とやりたくない。

さて、ここで少しだけ言葉を整理しておこうと思う。私は刈払い機で草を刈っていると書いたが、草刈りをするための草刈り機というものも存在する。
⚫︎刈払い(かりはらい)=山地や農地などで、伸びた草や不要な植物、かん木を刈り取って綺麗にする作業。刈払い機は強い切断力があるので、刃によっては5〜8cmの小枝を伐ることができ、山の中の狭い場所や、作業がしにくい場所で使うことができる。刃だけではなく、ナイロンコード(ひも)での刈払いも可能。
⚫︎草刈り=庭や公園などの一般的な場所で、伸びた草を刈る作業。草刈機は広範囲を効率的に刈ることが目的。
⚫︎下刈り(したがり)=植林した苗木の成長を助けるために、周囲の雑草や雑木を刈り取る作業。
桃太郎のしばかりの時代以前から、様々な農具が生み出されてきた。それらは時に武具として使われたとも言われる。狩猟道具を綯い交ぜにしながら、長い時を経て刈払い機やチェンソーは開発された。林業に携わっている人たち、山林の近くに住む人たち、里山を整備する人たち、用途によってどんな機械を使って手入れをするかは変わってくるのだが、刈払い機は、農地や田んぼの畔の草刈りや、山林の下刈り、どちらにも使えるため、多くの人がホームセンターで買い求める機械だ。私と同様「倉庫に眠っていて」とか「先代が放りっぱなしにしていて」という人は、案外多い。そしてメンテナンスされていないため、使うことじたいにハードルを高く感じる人も多いようだ。
刈払いは、作業か?労働か?活動か?

里山をはじめとした山林の下草を刈り取る”下刈り”は、とても大切な仕事である。特に人工林では、樹種の成長を促すためには、無くてはならない作業だ。みなさんがイメージする、公園や農地の草刈りとはちょっと違うかもしれないけれど、私の少しの経験からしても、全てが延長線上に続いているような気がする。どれも私たちが住んでいる地球を掃除したり、土地を豊かにする活動なのに、「仕事」だと認識されにくいなあと思う。
日々の糧のために行われてきた下刈りや刈払いの習慣は、姿を消してしまった。もはや、桃太郎に出てくるおじいさんはいない。現代では、それらの作業が「労働」に分類されてしまうからなのかな、とも思う。林業も同様で、3K(きつい、汚い、危険)や4K(+給料が少ない)というカテゴリーに括られて見られているのかもしれない。
山や農地の労働は、AIやロボットに、そして遠隔操作に変わっていくのだろうか? 現状と同様、退職後のシニアの営み、もしくはシルバー人材センターが担う仕事のままで過ぎていくんだろうか? 公共が担い、業者に発注するだけでいいんだろうか? 山に行けば行くほど、その問いは私自身に突き刺さってきた。
どこにいても、見ているのは草ばかり

こんなモヤモヤが頭の中にあるものだからか、街のあちこちで空き家の庭に伸びる雑草や、アスファルトの隙間から涙ぐましい努力で成長するセイタカアワダチソウをみるたびに、一人ため息をついてしまう。誰かに刈られるまで、この草たちは放っておかれるのかなぁ。そんな視線を家族や友人に話すたび、ちょっと驚かれる。というよりは、若干引かれている。たぶん一般の人が見る景色の中に、草は埋没してしまっているのだろう。目の中に入らないだけなのだと思う。見えてくるのが良い訳ではなく、単純に視線の解像度の違いだ。私が山へ通ううちに、そうなってしまっただけなのだ。だって、公園の木を見ると、どこから手入れしてやるといいかなあとついシミュレーションしてしまうし、木に絡みついている蔓をみると、可哀そうだなあと伐ってしまうから。これは完全に、師匠Nさんの影響だ。
そして私やお爺たちが、どこもかしこも刈ることは現実的ではないし、限界がある。そして「勝手に草を刈らないでほしい」とNさんは言われたことがあると言うし、「40年以上も言い続けている」けど、隣の庭の茫々と生えた木や草を伐ってくれないとこぼす、山のお婆の話も聞いた。
冷蔵庫で大切にとっておいた賞味期限切れのプリンを、家族の”善意”で勝手に捨てられたら怒るのと似ているかもなあ、と思ったりする。
まずは、やってみるかぁ。

そんなわけで、放置田んぼの草刈りにうんざりした私は、ちょこちょこ手入れするしかないか…と、山へ頻繁に通うようになっていった。メインは農地の草や雑木の手入れ。周囲の田んぼへ多大な迷惑をかけているという事実ももちろんだが、自分の持っている場所が荒れているというだけで、夢でうなされるようになってしまった(笑)。夢に出てくるのは汚い部屋。目覚めて一息つくたびに「よくあんな部屋を思い描けたなあ」と関心してしまうくらい、何パターンもの間取り、不要な物・ゴミの種類が毎回違う。自分の潜在意識であることは間違いないのだが、Nさんにこぼすと苦笑していた。
愛車の軽トラは山から1時間弱の実家に置いてあるのだが、駐車場が空いているのが近所で目立つようになってきたらしい。とうとう隣のお婆様から「どこに行ってるの?」と、声をかけられた。日頃から庭や畑仕事で外にいるから、疑問に思ったそうだ。
私が「山に行っているんです」と言った瞬間、そのお婆様の表情が変わった。「うちも山があるけれど、全然行けてなくて、ほかりっぱなし(放ったらかし)で。あなたのお爺さんが山へ行っていることを聞いたら、喜ぶわ。よく仕込まれたのねえ」と涙ながら話してくる。
いえいえ、祖父から指南されたことは一度もありません。そう思いつつ、こういう誤解はそのままにしておいてもいいかもなぁ。幻想も理想も、まずは飲み込んでみようと笑顔を返した。

山川 愛(やまかわ あい)
愛知県在住。公益財団法人かすがい市⺠文化財団プロデューサー。金沢美術工芸大学工業デザイン科を卒業後、アートマネジメントの領域で活動。同財団に入職後は、展覧会や演劇公演の企画・広報、昨今は自分史を始めとした市民との協業事業を担当。2021年から亡き祖父の山に入り、山主として自分に何ができるかを模索している。
あとがきコラム#9 山と朗読
柴田元幸さんが朗読するトマス・ハーディー

大学時代から、柴田元幸さんの翻訳本にはお世話になってきた。中でもアメリカ人作家 ポール・オースターの『ムーン・パレス』は何度読みふけったかわからない。当時の多感な美大生にとって「芸術とは理解するための手立てなのだ。世界に入り込み、そのなかに自分の場を見出す道なのだ」という一節には随分と励まされた。
そんな柴田さんは各地で朗読会を開催している。その理由は参加してすぐにわかった。文章を書く人ならわかると思うが、翻訳家は文を口ずさむ。声に出して読むことで、不自然さがないか、リズムがあるか、原文を代弁しているかを確認しているのだと思う。だから柴田さんにとって朗読は日課なのかもしれない。歌を聞いているような、お芝居を見ているような、題材によっては落語を聞いているような楽しい時間なのだ。
トマス・ハーディ作『老いたミセル・チャンドル』は、まだ本に収録されていないが、ホカホカの訳文だった。チャンドルお婆さんをめぐる悲喜交々が、私の山にまつわる様々な勘違いにも通じて、朗読を聞きながら思わず笑ったり、目を細めたり。100年前のイギリスの田舎の風景が、現在の日本の山の景色に通じるなんてことがあるんだなあ。柴田さんのおかげで、ハーディーという優しい故人に巡り合うことができた。
そんなハーディーのチャーミングな小品が詰めこまれた『ロングパドル人間模様』(ロングパドルは地名、葉々社/2024年)、おすすめです。
シリーズ「山って…何なん?」 と何度もつぶやくことから始まった、山主候補生の活動日記

「山って…何なん?」 と何度もつぶやくことから始まった、山主候補生の活動日記
祖父が残した言葉をきっかけに、山へ通いはじめた「私」。祖先が守ってきた山とは、何なのだろう。
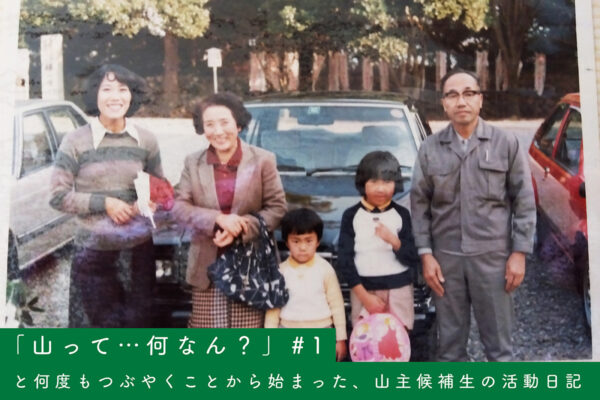
爺さまが残したもの
[新連載] 2020年の春、爺さまが亡くなった。最後の言葉は「山は、もう、いい」だった。

ところで…「山」ってどこにあるの?
祖父と過ごした思い出の山はどこにあるのだろう? 行けば「うちの山」ってわかるのだろうか?

山の境界を歩く(1)
静岡県浜松市の水窪町で出会ったのは、自伐林家に生まれ、山と共にいきてきた一人の若者だった。

山の境界を歩く(2)
山の境界を目指し、いよいよ山の中へ。道のない山面を必死で上がると、爺さまたちが守った山の姿があった。

山の境界を歩く(3)
相続する山がどこにあるのか、境界線がどこなのか。山を歩き、県庁を訪ねてわかってきたその全貌とは?

境界を知って、そして
山へ通うようになって3年、境界を歩いたからこそ見えてきた、次の道とは?
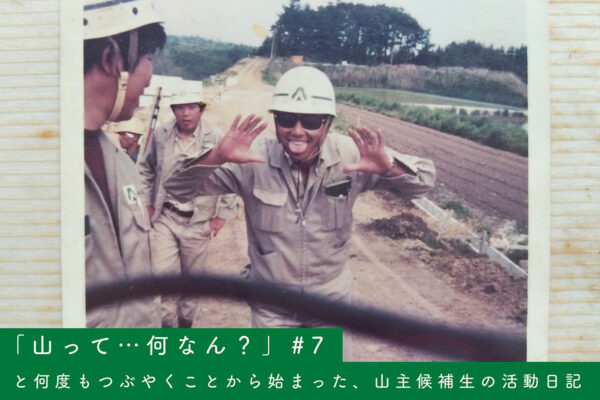
もう、欲しいものなんて無い
山を相続した私は、木を伐ることを学び始めた。その営みと共に、出会いや別れも訪れる。

草刈の技法、伐採のフーガ
山の人たちに受け入れてもらうために、試行錯誤する私。そして、聞こえてきた新たな“音”とは。



