我々の役に立つツル植物【前編】 簡単に作れる「紐」
里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4
前回までに、ツル植物の持つしたたかな戦略についてお話してきた。しかし、したたかとは言っても植物の世界だけの話。考えてみれば、それを利用する人間の方がもっとしたたかなのかもしれない。と、いうことで今回はツル植物の使いみち、という話題を。
誰にでもできるツル利用
ツル植物は、当然名前のようにツルをつくる植物である。ツルは見方を変えれば、「紐」であり、「ロープ」でもある。なので、ものを縛るのに用いることができる。幹とは違って節約してつくられているとはいえ、植物のつくるツルは、よじ登った先のかなりの高さについている葉まで水を運ぶという目的のために、強靱にできている。特に繊維を束ねて使っていて簡単には千切れない。人間が利用するロープも、繊維を撚り合わせてつくる。天然のツルも同じである。
アオツヅラフジを紐代りに使ってみる
身近にあってツルとして利用できそうな植物としてすぐ思い浮かぶのが、アオツヅラフジである。名前に「フジ」と入っているところに、丈夫なツルではないかという期待が持てる。実際にその辺にでかけて林縁を探すと、比較的簡単に見つかる(写真1)。
-1024x683.jpg)
よく見ると未熟なブドウのような実がついている。これが熟すと青黒くなり、ますますブドウのように見えてくる(写真2)。ブドウとの違いは個々の果実(粒)が房状に長くたれ下がらずに、塊のようにつくところである。
-1024x768.jpg)
いかにも美味しそうだが、有毒植物なので食べない方が無難だ。熟した実を口に入れてみたことがあるが(よい子は真似しないでいただきたい)、軽い甘みのあとにえぐみがきたので吐き出した。やはり見た目だけのようである。全草にアルカロイド系の毒を持ち、大量に摂取すると呼吸中枢や心臓などに悪影響が出る可能性がある。子供が間違って食べないよう注意が必要だ。一方で、ツルや根を乾燥したものは、腎臓病の薬として用いられるらしい。ほかにも解熱、利尿、鎮痛、血圧降下などの作用があるそうだが、何せ有毒植物である。薬と毒は紙一重などというが、素人が安易に手を出すと危険であろう。
とはいえ、紐代わりにものを縛る分には構うまい。そこで、このアオツヅラフジのツルがビニール紐の代わりにならないか試してみた。目の前に縛りたいものがあるのに、ついうっかりビニール紐を忘れてしまったとき、環境中にプラスチック製品をまき散らしたくないとき、モノを知っている自分を他人に自慢したいときなどに、役に立ちそうである。まずはツルを切り取って(写真3)その後ついている葉をすべてむしりとり、枝の束を縛ってみる(写真4)。意外としっかりしていて、普通に縛ることができる。短時間だけ持ち運ぶには十分役立ちそうである。
-1024x683.jpg)
-1024x683.jpg)
ヒメコウゾでも縛れるか
不安定なので、もう一箇所縛ろうと思ったが、ツルの長さが足りない。そこで今度は別の植物を使ってみることにした。それが近くに生えていたヒメコウゾである(写真5)。
-edited-scaled.jpg)
葉っぱを見ると切れ込みがエグいが、これは虫に食われたのではなく、元からこうなんである。その証拠にどの葉も同じような形で切れ込んでいる。木が大きくなると切れ込みのない葉が多くなることから、背の低い環境で有利な点が、切れ込んだ葉っぱにはあるのだと推測できる。事実カクレミノなど、最初は切れ込んだ葉をつけているが、木が大きくなると切れ込みが入らなくなる樹木は他にもある(写真6)。
-1024x930.jpg)
樹木が小さい時と大きいときではまるで別の植物のような変貌っぷりだ。一つの個体が異なったタイプの葉をつけるとき、これを異形葉(heterophyll)という。ヒメコウゾもそのひとつである。なぜこんなことをするのか、ヒメコウゾに尋ねてみないと分からないが、林内環境で葉面境界層を薄くしてガス交換を円滑に行うための複雑な形だ、という仮説もあるらしい。
ヒメコウゾはツル植物ではないのでは? というむきもあるだろう。まったくもってその通りである。なぜならヒメコウゾは他人(他の植物)に巻きついたりしないからだ。ただダラダラと長く枝を伸ばし続けるだけである。巻きつくと言うよりは、むしろ巻きつかれる側の立場の植物だ。園芸の世界ではこういった植物を半ツル性と呼ぶこともあるらしく、人間が誘導して樹形を整えるようである。
まずは皮をむいて
話をヒメコウゾでモノを縛る方に戻そう。葉っぱはアオツヅラフジ同様むしってしまうとして、そのままでは縛るのに苦労しそうである。なぜなら材が硬くてそう簡単に曲がりそうにないからだ。そこで皮をむいてみることにする。ヒメコウゾの枝の切り口から爪で切れ目を入れて一気に引っ張ると面白いように皮がむける(写真7)。一般的な和紙の材料として最も使われているのが、このヒメコウゾと、カジノキという樹木の雑種であるコウゾであるが、このむいた皮の方を、和紙の原料に用いる。残った白い材は廃棄物扱いだ。昔この白い材とたこ糸でおもちゃの弓をつくってみたことがある。簡単につくれるが、遊びで使うには十分なものができた。利用というほどのことではないが、試してみると面白いかもしれない。
-1024x683.jpg)
丈夫な靭皮の利用方法
このむいた方の皮の靱皮(じんぴ)組織はしっかりした繊維の集合であり、一度ばらばらにして漉き直すことによって丈夫な和紙ができる。ちなみに国産の和紙でよく用いられてきた樹木には、ほかにミツマタとガンピがある。ガンピ(写真8)はコウゾやミツマタに比べて繊維が短く、繊細な風合いの和紙ができる一方で漉くのに高度な技術を必要とすること、ガンピの自生する場所が減り、栽培も難しいため原料の供給が難しいことなどから、雁皮紙(がんぴし)を目にする機会は減っている。一方でミツマタ(写真9)は繊維が長く、丈夫で耐久性の高い紙ができることから、みなさんご存知のお札に使われている。ちなみにアメリカのドル紙幣には綿が使われているそうだ。
ミツマタは元々中国原産の植物で、日本の山野に自生しているものは持ち込まれたものが野生化したものであろう。日本の焼き畑は数年間野菜や雑穀を種類を変えて決まった順番で栽培するのだが、最後に植栽される植物は樹木であることが多い。その中には、コウゾやミツマタも含まれていたらしい。商品作物として重要だったに違いない。
ヒメコウゾの皮をむくのは気持ちいい。子供たちにむかせてみたことがあるが、概ね大好評であった。「いつまでもむいてられる」「もっとないの?」等の意見をいただいた記憶がある。
ちなみに和紙の生産のためにコウゾをむく場合は、一度釜で蒸してからの作業になるのだが、那須楮(なすこうぞ)の生産を行っている茨城県大子町では、釜に入れる前にコウゾの束をその年に伸びたクズのツルを使って縛り上げるそうだ。非常に丈夫だし、釜で蒸しても丈夫で何度も使えるということだ。
いよいよ縛ってみる
またまた話を戻さなくては。
さて、むいたヒメコウゾの靱皮を使って枝の束を縛ってついでに取っ手もつけてみる(写真10)。あれれ? 思ったよりしっかりしているではないか。何かお洒落ですらある。思いつきでやってみた割には。もっともオジサンが持ってみたところで到底お洒落には見えないだろうが。
-1024x683.jpg)
そういえば、アオツヅラフジは琵琶湖で鴨猟をする際に使われていたそうである。浮き袋をつけて水面に浮かべておくと、鴨が足をとられて飛び立てなくなる。トリモチを使えばさらに確実だ。これも細い割にはしっかりしたアオツヅラフジのツルの特性が役に立っているのではないだろうか。
元から紐みたいなツル植物のツルはものを縛ったり吊したりするにはむいているようである。特別な技術無く誰にでもすぐに使える使い方だが、どのツル植物が使いやすいか、とか、その辺に生えていてすぐ見つかるのはどれか、どの部分が丈夫か、など考えてみると奥が深いかもしれない。
(後編に続く)
今回登場した植物

著者:柳沢 直(やなぎさわ なお)
岐阜県立森林文化アカデミー教授。
京都府舞鶴市出身。京都大学理学部卒業。京都大学生態学研究センターにて、里山をフィールドに樹木の生態を研究。博士(理学)。専門は植物生態学。地質と植生の関係に興味がある。2001年より現職。風土と人々の暮らしが育んできた岐阜県の自然が大好きだが、最近もの忘れが止まらない。原稿の〆切は言うに及ばず日本語も忘れかけている。このまま連載続けられるのか…?
シリーズ里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜
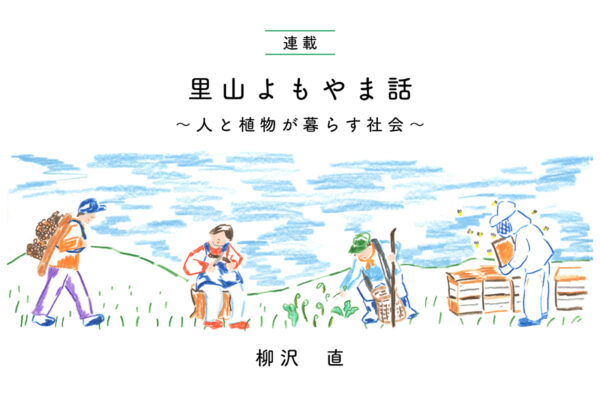
里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜
人が手を加えることで環境が維持されてきた「里山」(さとやま)そこで人や植物、獣たちはどのように暮らしているのでしょうか? …
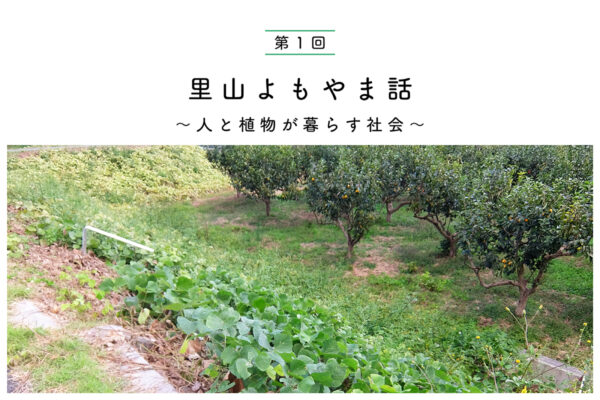
最強のツル植物① 空き地の暴れん坊将軍 “クズ”
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #1] 植物生態学者・柳沢直教授の新連載がスタート!
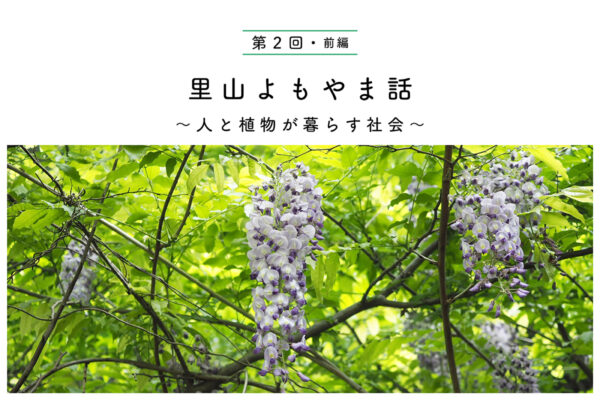
最強のツル植物②【前編】 美味い野生植物“フジ”
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2] 最強のツル植物フジ!じつはフジって美味しいんです
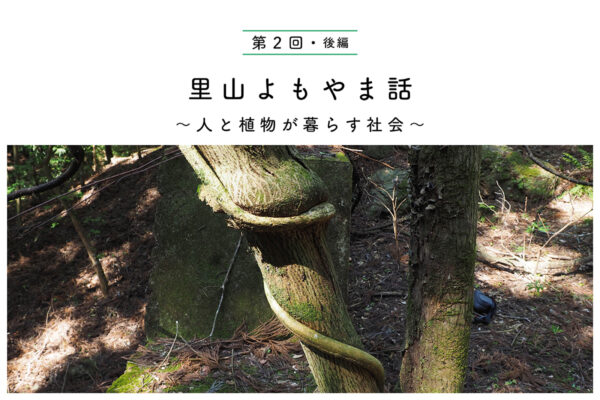
最強のツル植物②【後編】 林縁の格闘家“フジ”
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2] 最強のツル植物フジの最強たる所以は?
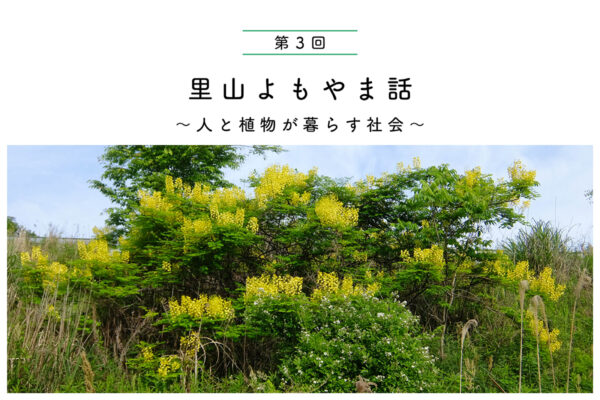
我々に身近なツル植物 よじ登ったその先に・・・
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #3] 引き続き「ツル植物」について
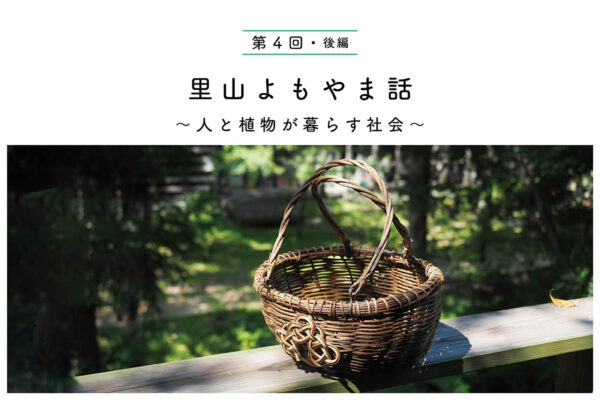
我々の役に立つツル植物【後編】 簡単には作れない「篭(かご)」
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4] 熟練技術が光るツルのカゴたち
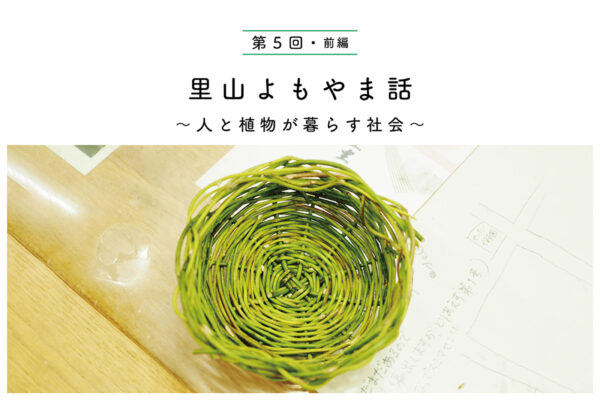
ツル植物で手仕事してみる【前編】 アオツヅラフジでカゴづくり
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #5] ツルを採集して編んでみる

ツル植物で手仕事してみる【後編】 サルトリイバラで箸づくり
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #5] ツル植物でお箸が作れる?
関連記事

春は野草を摘みに 〜柳沢教授の有用植物実習〜 ②採集編
食べられる野草を探して、春の里山へと出かけます。さてどんな植物が見つかるでしょうか?

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~
木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

多様な価値観に触れ、理想の森を考える。 岐阜県立森林文化アカデミー
[学校で森を学ぶ人たち] 森林や木材に関わるさまざまな分野の人が集まる岐阜県立森林文化アカデミーで学ぶ人に会いに行ってきました。
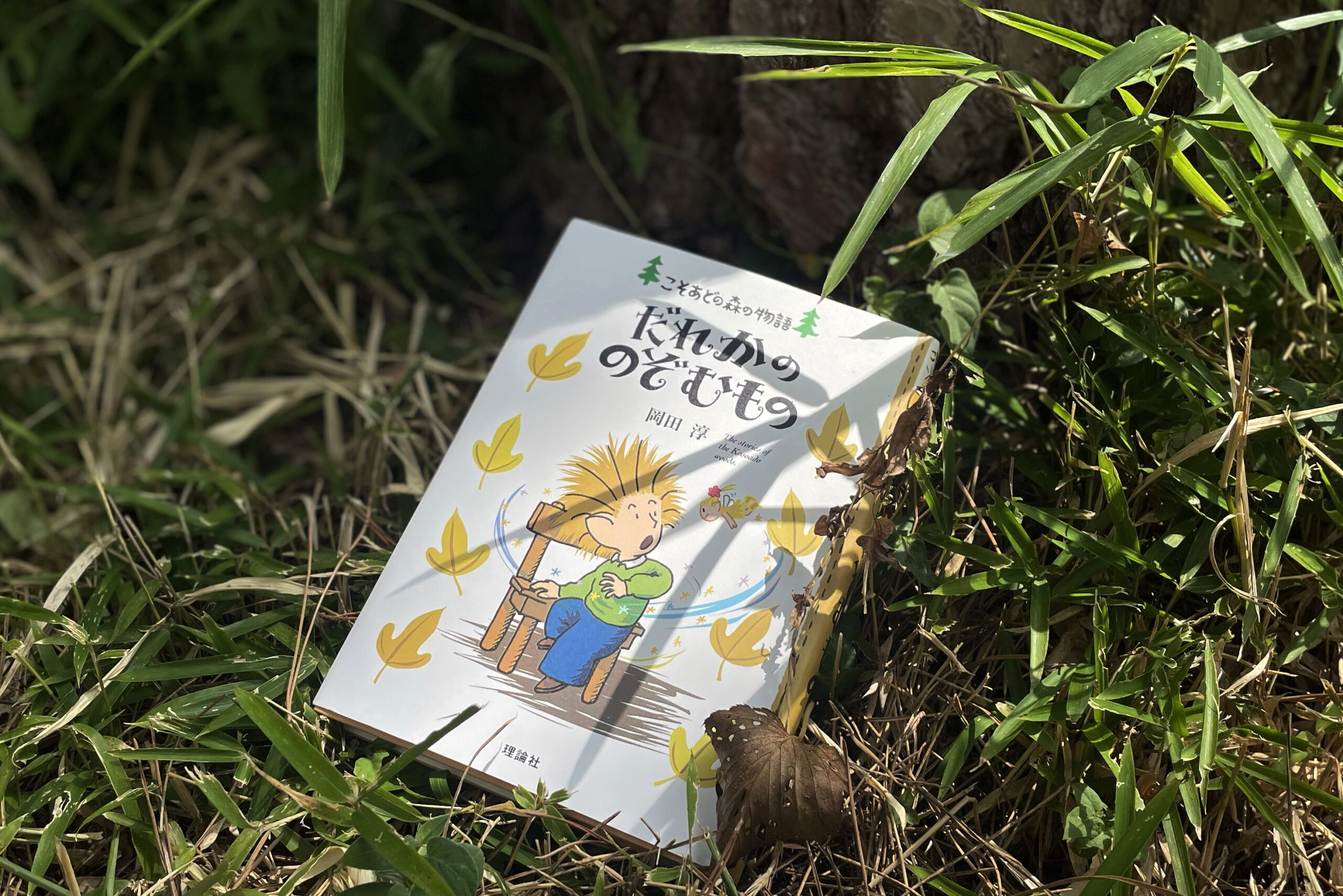
新林連載者がすすめる森にまつわる本
[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画
[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画


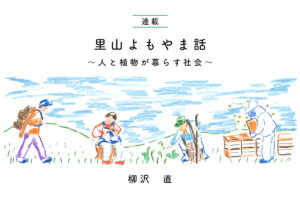
-edited.jpg)
-edited-scaled.jpg)



