我々の役に立つツル植物【後編】 簡単には作れない「篭(かご)」
里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4
ツルを使った細工物の定番「篭(かご)」
植物のツルを使って作る細工物、といえば篭(かご)である。素材のままを使って編み上げるとはいえ、編むには熟練の技術が必要である。私ごときでは到底作ることができないので、また自分で体験してできるようになったらその過程を報告しようと思う。
オオツヅラフジの篭
-1024x683.jpg)
まずは篭とその材料を紹介しよう。こちらの篭(写真1)は岐阜県揖斐川町で作っておられる方から購入した。側面の模様がキュートである(写真2)。素材のままを使って、とはいうものの、編みやすくするような加工は必要かもしれないし、そもそも採集の時点で適したものを探さなくてはいけないであろう。そのあたりいつかじっくり聞いてみたいものである。技術を持った方はだいたいご高齢なので、悠長にはしていられないかもしれないが。
-1024x683.jpg)
この篭の素材は前編で登場したアオツヅラフジの仲間でオオツヅラフジという。こちらはアオツヅラフジのように里山の林縁に多いというよりも、山の奥の方に自生していて、そう簡単には出会えない。以前紹介したフジと同じく、林内を葉をつけずにツルだけで這い回っていたりするので、知らないと何の植物だか頭を悩ます羽目になる。郡上市の山中でこの植物と初めて出会ったとき、何の植物だかわからずツルの一部分だけを持ち帰って、あとで葉っぱが出ないかな、と、プランターに挿しておいたことがある。すっかり忘れていたら、翌春になって芽吹いているのを発見してようやく何かわかった。オオツヅラフジだったのである。芽吹きの葉っぱは瑞々しい質感で葉も乳児の手のように可愛らしい(写真3)。ちなみに別名のツヅラフジは、つづらをこの植物のツルで編んだことによるという。
-899x1024.jpg)
オオツヅラフジもアオツヅラフジ同様薬草であると同時に有毒植物である。どの程度成長した部分を用いるかということもあるのだろうが、オオツヅラフジのツルはアオツヅラフジよりもしっかりした印象である。篭もしっかりとしていて、摘んできた山菜を入れておくのによさそうだ。
アケビのカゴ
-1024x683.jpg)
もうひとつの篭は、野趣溢れる感じの一品だ(写真4)。材料はアケビのツルである。よく見ると、まるで自生するアケビがお互いに絡んだような感じにも見える。手仕事によって作られる細工物には個性が感じられ、見ていて飽きない。使ってみたらどうだろうなどと思いつつも、高価な借り物なので使用感は試さず撮影だけして返却した。こういったものを自分で作れるようになったらきっと楽しいに違いない。
アケビもまた、様々な用途で使われてきた有用な植物である。まず頭に浮かぶのは、紫色の甘い果実である(写真5)。紫、とは言ったが紫なのは皮だけであり、食べる部分は白いイモムシのような形をしている(写真6)。学生のときに同級生に勧めたが、「イモムシみたいで嫌!」と拒否反応をおこされてしまった。お味の方は・・・酸味がないので取り立てて美味しいという訳では無いのだが(※個人の感想です)、舌に絡みつく上品な甘さは、甘味の限られていた古代の日本人にとってはさぞかし美味であったに違いない。などと想像しつつ、口に含んだ大量の種を口から連射してあたりにばらまくのだ。庭に播けばそのうちあたり一面アケビだらけになるかと思いきや、そうでもない。しかし、職場のある美濃市では、林縁や植え込み、生け垣などに絡んでいることも多いので、私のようにたらふく食べた鳥が一休みしながらばらまいていった種子があちらこちらで芽を出しているに相違ない。
ほかにもアケビの若いツルの先は春先に摘んで山菜とする。紫色の皮も、肉を詰めて天ぷらにしたり、ぬか床や味噌に漬けて食べたりもする。茎(ツル)に含まれる薬効成分には胃液の分泌抑制や、ストレス潰瘍に対する効果があるらしい。その他利尿作用や消炎など多くの作用をもち、「木通」として漢方薬に配合されている。
ヤマブドウの篭
-edited-scaled.jpg)
最後に紹介するのは、この手の細工物の中では王様(女王様?)と目されるヤマブドウのツルで編んだ篭である(写真7)。篭と言うよりはバッグと言った方がよいかもしれない。素敵である。細部にわたってとても美しい(写真8、9)。
-1024x683.jpg)
-1024x683.jpg)
持った感じも柔らかく、手にしっとりと馴染む。お値段の方も日本円で6桁はくだらないくらいの高級品だが、製作の手間を考えるときっと妥当なのだろうと思う。材料のツルの採取にしても1年のうち限られた期間にしか適したものがとれないという。こちらも大急ぎで撮影を済ませ、持ち主に返却した。日常使いでこそきっと手に馴染んで風合いも良くなっていくのだろうが、おっかなくて普段使いできないというこの矛盾。私にはまだまだ分不相応な工芸品かもしれない。
ヤマブドウが豊富にある地域は
最後にヤマブドウを紹介しよう。北海道に行ったときに、道東で道ばたに茂っているヤマブドウを見た(写真10)。
-1024x683.jpg)
ヤマブドウは、森林文化アカデミーのある濃尾平野北端のあたりでは珍しく、身近にはみられない植物である。気分的には希少性が感じられる。しかも実は食べられるし、ジュースやジャムをつくることも可能である(ヤマブドウを使ったお酒を酒類製造免許を受けずに製造するのは違法行為)。なんてゴージャスな、北海道は贅沢な土地であることよ、と感動した。しかし、行く先々でヤマブドウを目にするにつけ、当初の感動は薄れてきた。有名な旭山動物園でも園舎の檻に我が物顔で絡んでいるのは、やはりヤマブドウである(写真11)。
-1024x683.jpg)
一見するとお洒落にブドウを生やしたようにも見えるが、野生で生えて居る様子を見た後では、手入れをサボっていたら蔓延ってしまったのではないか、という疑念を禁じ得ない。いずれにせよ北海道に住んでいたらヤマブドウで一夏楽しめるのに、と、羨ましく思う。
おわりに
生活に使う道具の材料は生活圏内の自然から採集されている。そのため、それぞれの風土にあってよそにはない植物がしばしば使われることになる。ヤマブドウやオオツヅラフジはその好例であろう。現代のような商品経済社会でグローバル化が進むと、PPテープなどの石油製品が幅をきかせ、ちょっとしたものにこそ使われてきた身近な自然からの素材は影を潜めてしまった。実に残念である。まずは遊びでもいい。身近な植物を使ってなにか試みることができれば、ささやかな充足感とともに、地域の自然や資源に目が向くのではないかと思う。
今回登場した植物

著者:柳沢 直(やなぎさわ なお)
岐阜県立森林文化アカデミー教授。
京都府舞鶴市出身。京都大学理学部卒業。京都大学生態学研究センターにて、里山をフィールドに樹木の生態を研究。博士(理学)。専門は植物生態学。地質と植生の関係に興味がある。2001年より現職。風土と人々の暮らしが育んできた岐阜県の自然が大好きだが、最近もの忘れが止まらない。原稿の〆切は言うに及ばず日本語も忘れかけている。このまま連載続けられるのか…?
シリーズ里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜
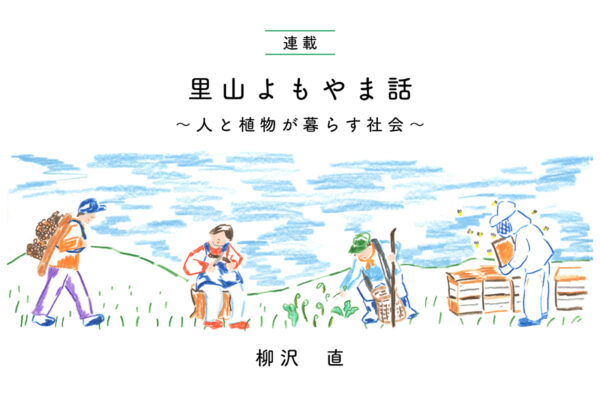
里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜
人が手を加えることで環境が維持されてきた「里山」(さとやま)そこで人や植物、獣たちはどのように暮らしているのでしょうか? …
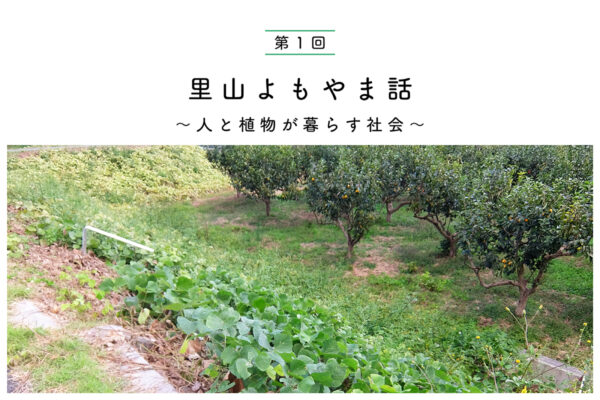
最強のツル植物① 空き地の暴れん坊将軍 “クズ”
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #1] 植物生態学者・柳沢直教授の新連載がスタート!
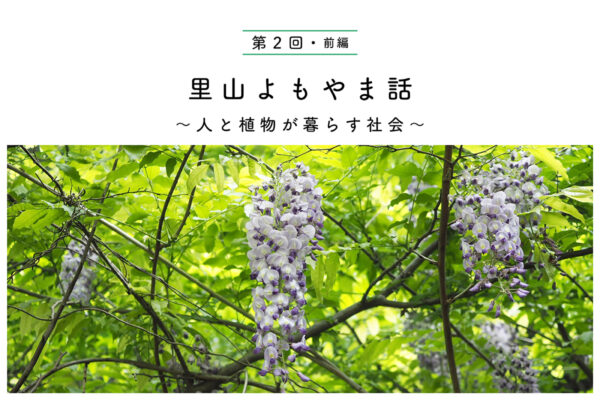
最強のツル植物②【前編】 美味い野生植物“フジ”
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2] 最強のツル植物フジ!じつはフジって美味しいんです
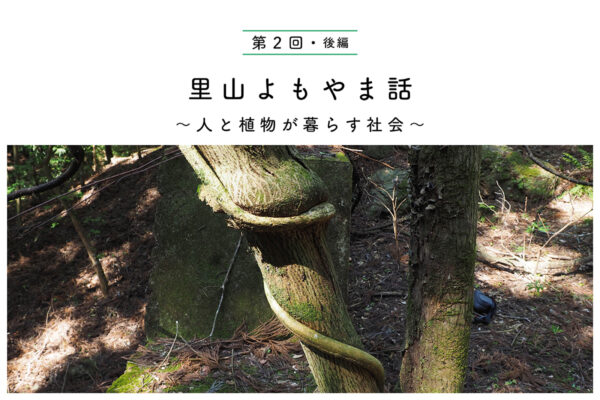
最強のツル植物②【後編】 林縁の格闘家“フジ”
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #2] 最強のツル植物フジの最強たる所以は?
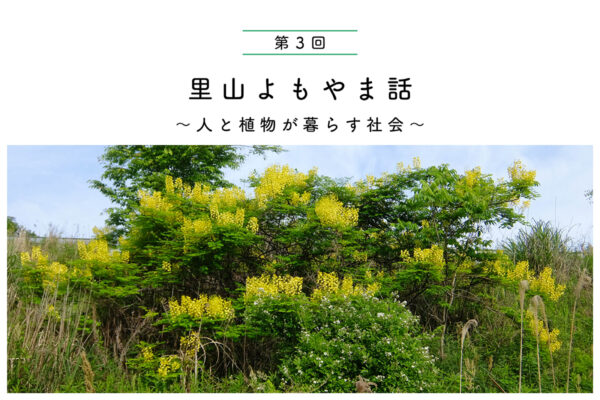
我々に身近なツル植物 よじ登ったその先に・・・
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #3] 引き続き「ツル植物」について
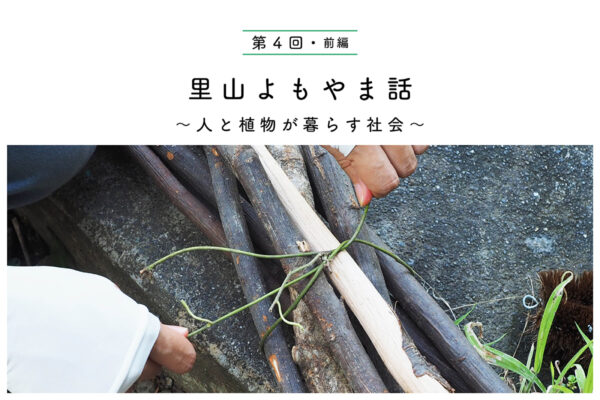
我々の役に立つツル植物【前編】 簡単に作れる「紐」
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #4] まだまだ「ツル植物」について
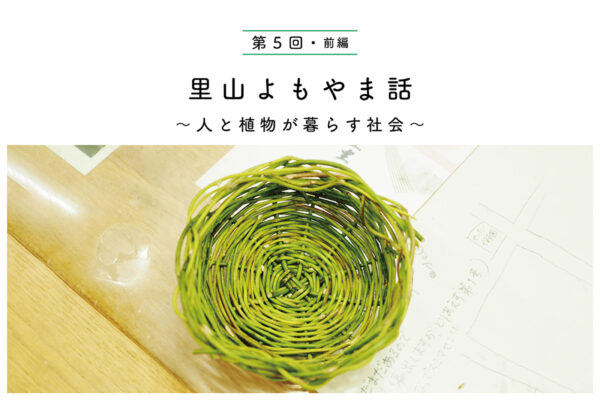
ツル植物で手仕事してみる【前編】 アオツヅラフジでカゴづくり
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #5] ツルを採集して編んでみる

ツル植物で手仕事してみる【後編】 サルトリイバラで箸づくり
[里山よもやま話 〜人と植物が暮らす社会〜 #5] ツル植物でお箸が作れる?
関連記事

春は野草を摘みに 〜柳沢教授の有用植物実習〜 ③実食編
摘んだ野草を調理して、いよいよ実食。天ぷら、おひたし、よもぎ餅と、春の味覚が並びました。

森の舞台の役者たち ~植物の暮らし拝見~
木を見て森を見ず? いやいや、うっかり見過ごしてしまうような森の小さな草木たちも森林という舞台で懸命に生きているのです。森を足元から見てみると、そこには魅力あふれる役者たちが暮らしていました。

多様な価値観に触れ、理想の森を考える。 岐阜県立森林文化アカデミー
[学校で森を学ぶ人たち] 森林や木材に関わるさまざまな分野の人が集まる岐阜県立森林文化アカデミーで学ぶ人に会いに行ってきました。
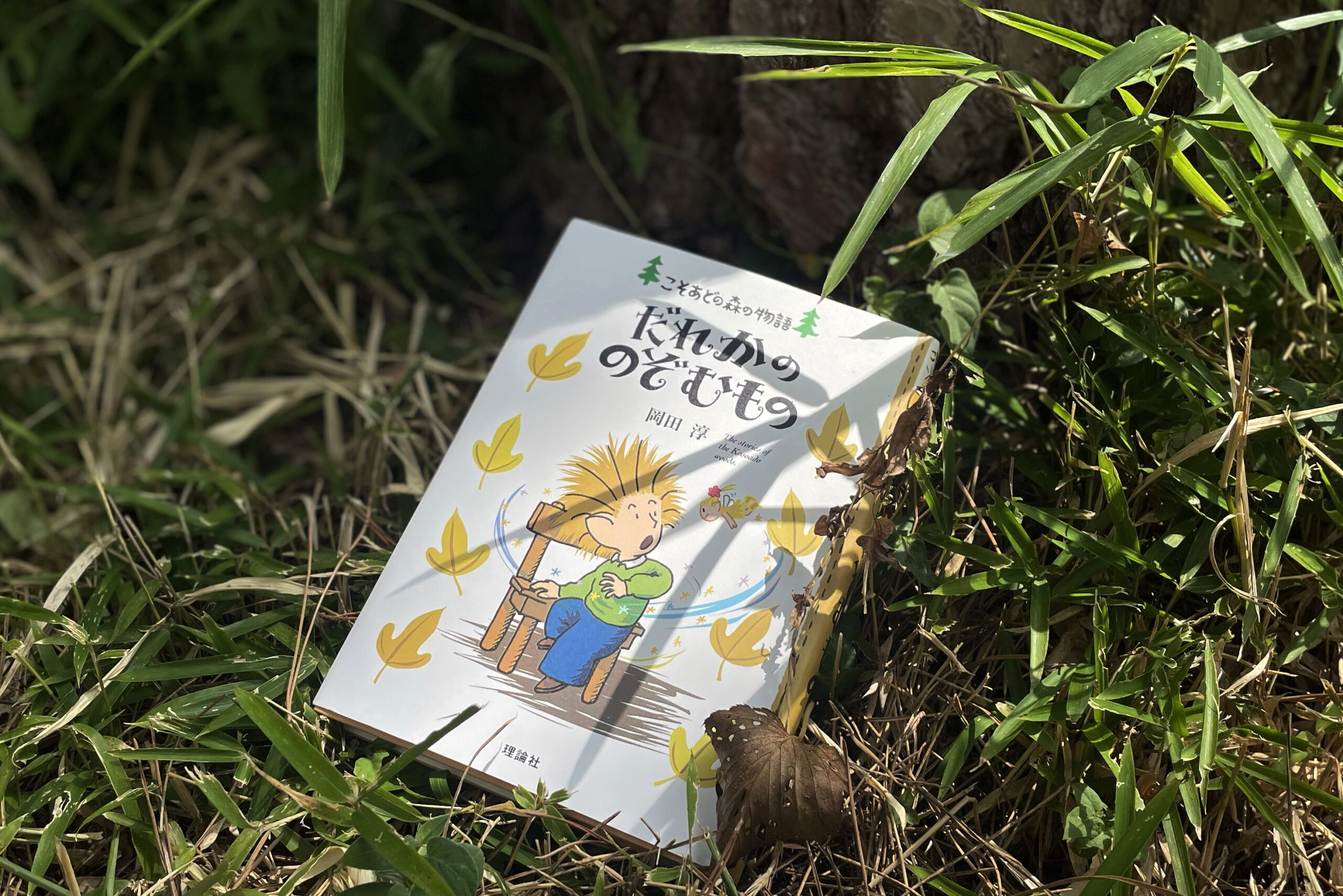
新林連載者がすすめる森にまつわる本
[森のほんだな #1] 森を題材にした本、日々の活動とリンクして森を感じた本...それぞれの“森にまつわる”本

新林連載者がすすめる森にまつわる映画
[森のえいがかん #1] 森が題材の映画、日々の活動とリンクして森を感じる映画...それぞれの視点による“森にまつわる”映画


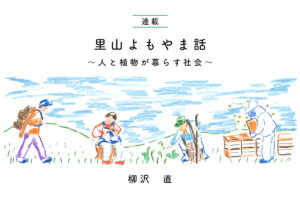
-1024x683.jpg)
-edited.jpg)


